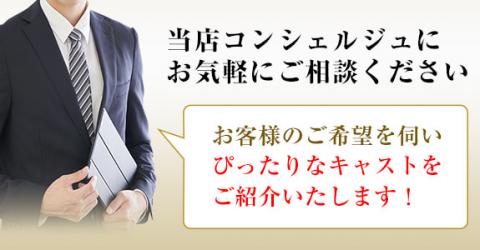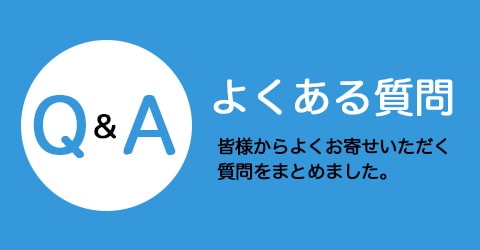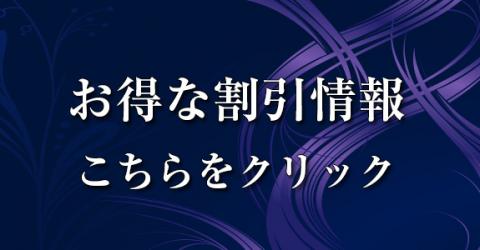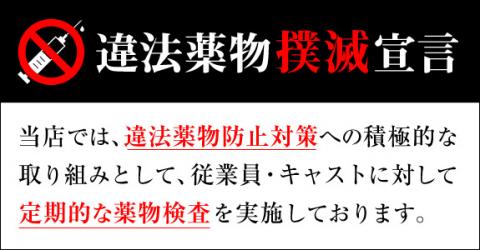モノのこと
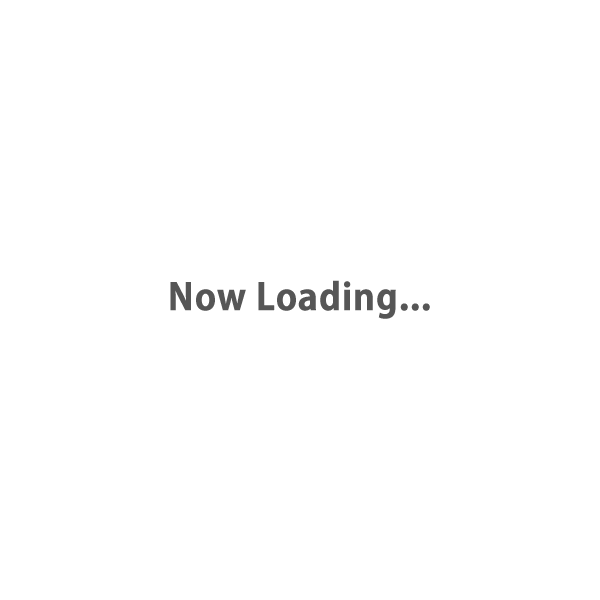
こんばんは✨
夕方に見た天気予報では、今度の土曜日深夜から日曜日にかけては雨に雪が混じるかも…
とのことでした❄️
それに明日からはだいぶ冷えるみたいですね
一方で沖縄はまだ25℃ぐらいあるとのことで驚きです!🏖️
明日15:00〜24:00、明後日13:00〜23:00で出勤します
お時間があればぜひ^^
………………………………………………………
今回は羽田圭介「滅私」です
主人公は「ミニマリスト」としての自らのライフスタイルをネットで発信し、ライター業と投資で生計を立てる冴津という男
家にあるのは必要最低限の家具や家電だけで、その他の余分なものは持たない暮らしを実践していました
そんなある日、冴津の過去を知る男が現れたことをきっかけに彼の生活は少しずつ狂い出してゆきます…
「ミニマリスト」という言葉が人口に膾炙するようになったのは凡そ2010年以降のことのようです
そうしたライフスタイルを持て囃すメディアやSNSの投稿などを目にする度に、私はなんとなく違和感を抱いてきました( ´ー`)
モノが少ないことが、そんなに素晴らしいことには思えないのです…
現代の行き過ぎた消費社会や物質主義に対するアンチテーゼとして日々の生活にミニマリズムを取り入れることは、物欲やそれに由来する欠乏感からの解放にはならない気がします
日常から社会活動を維持するのに必要なモノ以外のあらゆる所持品を切り捨てるという行為は最も簡単かつ劇的に生活を変化させるかもしれませんが、「ミニマリスト」という思想への依存や、そういうライフスタイルへの執着は新たな苦しみの始まりのように思えます
より良い人生を送るのに必要なのは、他人のミニマリスト生活を真似してモノを捨てまくるという表面的な行為ではなく、自分自身で人生の軸となる思考を探すことではないでしょうか💭
2025/12/11 20:40